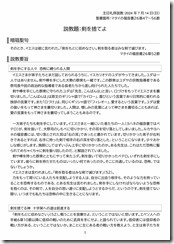- 主日礼拝説教:2024年7月14日(日)
- 聖書箇所:マタイの福音書26章47~56節
- 説教題:剣を捨てよ
暗唱聖句
そのとき、イエスは彼に言われた。「剣をもとに収めなさい。剣を取る者はみな剣で滅びます。
マタイの福音書26章52節
説教音声
説教要旨
剣を手にする人々 恐怖に縛られる人間
イエスさまが弟子たちとまだ話しておられるうちに、イスカリオテのユダがやってきました。ユダは一人ではありません。剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒です。この群衆はユダヤの宗教指導者である祭司長や民の政治的な指導者である長老たちから差し向けられた人たちでした。
剣や棒を手にした群衆に守られたユダは「先生、こんばんは」と言い、口づけをもってイエスさまを裏切りました。「こんばんは」は原文のギリシャ語で「カイロー」、喜びという言葉であり日常的に使われる挨拶の言葉です。また「口づけ」は、同じくギリシャ語で「フィレオー」、愛するという言葉です。ユダは愛の装いをもって神さまを裏切りました。人間は、憎しみの言葉によって神さまを裏切ることもあれば、愛の言葉をもって神さまを裏切ってしまうこともあるのです。
一方弟子たちも剣を手にしています。イエスさまと一緒にいた者たちの一人(ヨハネの福音書ではペテロ)が、剣を抜いて、大祭司のしもべに切りかかり、その耳を切り落としてしまいました。ルカやヨハネの福音書には、切り落とされた耳は「右の耳」であったと書かれています。切りかかった弟子が右利きであるとすれば、右手に持った剣で相手の右の耳を切り落とした、ということになります。少々おかしな感じがします。漁師にしてはずいぶん上手に切りかかったのか。ある先生は、これはただ恐怖に駆られてめちゃくちゃに剣を振り回したのだ、と解説されていました。
剣や棒を持った群衆とともにやって来たユダ。剣を抜いて切りかかったペテロ。いずれも剣を手にしています。彼らに剣を持たせたものはいったい何であったのか。そこに共通しているのは、恐怖、ではないでしょうか。
イエスさまは言われました。「剣を取る者はみな剣で滅びます」(52)。
力をもって周りにいる人たちを支配しようする人は、自分に出会う相手も、そのような力を持っていることを恐怖するものである、とある先生は言われました。剣を手にしなければならないような恐怖を抱くのは、その剣で、人を自分の思い通りに支配しようとするからだ、というのです。剣を捨てない限り、いつまでも私たちは恐怖の中に生きることになります。
剣を捨てる神 十字架への道は前進する
「剣をもとに収めなさい」(52)。戦うことを放棄せよ、ということではないと思います。エペソ人への手紙6章10節以降に信仰の戦いのために武具を手にせよ、と語られています。信仰者には信仰者の戦い方がある、ということではないか。まことに主にある者の戦い方を教えよう、と主は弟子たちを招こうとしておられるのです。
イエスさまはユダに向かって「友よ、あなたがしようとしていることをしなさい」と言われました。主はすべてをご存じで、ユダの裏切りを受け止めて十字架への道を進もうとしておられます。
ヨハネの福音書にはイエスさま逮捕の様子が次のように書かれています。
「イエスはご自分に起ころうとしていることをすべて知っておられたので、進み出て、『だれを捜しているのか』と彼らに言われた。彼らは『ナザレ人イエスを』と答えた。イエスは彼らに『わたしがそれだ』と言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒に立っていた。イエスが彼らに『わたしがそれだ』と言われたとき、彼らは後ずさりし、地に倒れた。」(ヨハネ18章4~6節)
ここには神の真理の力が如何に圧倒的なものであるのかが明らかにされています
またペテロには次のように語られました。
「それとも、わたしが父にお願いして、十二軍団よりも多くの御使いを、今すぐわたしの配下に置いていただくことが、できないと思うのですか。」(53)
「12軍団よりも多くの御使い」。12軍団とは「レギオン」という言葉で、当時6千人編成の軍隊をさした言葉だそうです。それほどの戦力を今すぐに配下に置くことが可能な主が、そうはなさらないで、聖書に書かれている通りに、すなわち神さまのみこころのままに自らをゆだねていこうとされる。あるいは全能の力をお持ちだからこそ、それを放棄することができる真の強さ。そこに主にある者の戦い方が明らかにされています。
弟子たちに見捨てられたイエスさまは、私たちを、そしてすべての人を救うために、一人黙々と十字架への道を進まれます。主にある者は、この主に守られています。武器を手にして、いたずらに振り回さなければならないような恐怖から解放され、主にある絶対的な平安の中に、すべてを委ねていきます。
エペソ人への手紙6章に信仰の武具として記されているのは、「真理の帯」「正義の胸当て」「平和の福音」「信仰の盾」「救いのかぶと」「御霊の剣、すなわち神のことば」「祈りと願い」。おおよそこの世の力とは無縁のもの、この世の価値観からは武具とは言えないようなものです。しかしここにこそ主に委ねることを知っている者の戦い方が明らかにされています。
右耳を切り落とされた大祭司のしもべをイエスさまはその場でいやされました。ヨハネの福音書18章10節には、その名が「マルコスであった」と記されています。おそらく福音書の書かれた時代には教会の仲間となっていたのでしょう。自らの耳を切り落としたペテロのいる教会の仲間となった。人間的には考えられないことです。しかしイエスさまとのこの強烈な出会いは、マルコスに救いの道を開き、隣人との新しい生き方を開いたのだと思います。剣を手にした人たちによってではなく、すべてを父なる神さまにお委ねし全き平安の中に十字架に向かわれる主イエスさまこそ、救いへの道です。
「イエスは彼に言われた。『わたしが道であり、真理であり、いのちなのです。わたしを通してでなければ、だれも父のみもとに行くことはできません。』」
(ヨハネ14章6節)
祈り
あらゆる恐れから私たちを解放してください。剣を捨てて十字架に向かわれる主の全き自由を教えてください。あなたを見上げながら、信仰の良き戦いを戦うことができるように、真理、正義、平和、信仰、救い、神のことば、そして何よりも祈りに生かしてください。