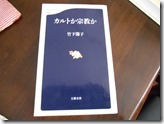日本のカトリックでは、このような日本における「宗教」への不信に対する神学的立場を明確にしようとの試みがなされている。組織的なものはないが、1995年にカルト宗教によるテロリズムが発覚した後、上智大学神学部部長でイエズス会の百瀬神父が「宗教とカルトの見分け方」というテーマで講演を行った。
そこで引かれたのは、聖書の中でイエスが悪魔に誘惑されるシーンだ。このマタイ伝(4―1~11)が書かれた時代(紀元80年前後)、すでに、地中海ギリシア語世界ではカルト宗教が林立していた。悪魔の誘惑のエピソードは、カルト宗教の誘惑に対するキリスト教の答えだといってもいい。
イエスは、公的な活動をする前に、一人荒野に出て40日間の断食をする。空腹になったところで悪魔がやってきて、「もしあなたが神の子であるなら、これらの石がパンになるように命じてごらんなさい」と誘惑した。イエスは「人はパンのみにて生きるものにあらず」(神の口から出るひとつひとつの言葉で生きるものである、と続く)という有名な言葉で答えて誘惑を退ける。
さらに、悪魔はイエスを宮の頂上に立たせて、「もしあなたが神の子であるなら、下へ飛び降りてごらんなさい」(落ちても天使が助けてくれるはずだから)と誘惑し、イエスは、旧約聖書の『申命記』の言葉(6―16)を引いて、「主なるあなたの神を試みてはならない」と言って退けた。
最後に、悪魔はイエスにこの世のすべての国々と栄華を見せて、「もしあなたがひれ伏してわたしを拝むならこれらのものをみなあなたにあげましょう」と誘惑した。イエスは、「サタンよ、退け。『主なるあなたの神を拝し、ただ神のみ仕えよ』(申命記6―13)と書いてある」と拒否した。
この三つは、それぞれカルトによる「現世利益」の誘惑、「超能力」の誘惑、「偶像崇拝」の誘惑を表している。イエスの答えは、人は自分の力のみで自己実現を図ってはならないし、富、知恵、自己実現を、礼拝すべき偶像にしてはならないということだ。人が人生の中でもっとも大切にしているいろいろなことでも、それを偶像にしてしまうと、そもそもその「人生」を反対側から成り立たせている「死」を拒否することにつながる。それでは「死」をも含めた人生を全的に受け入れることにはならない。竹下節子、『カルトか宗教か』、文藝春秋、1999年11月20日、67ページf。
私はプロテスタント教会の信仰を持つものですが、このカトリック教会の百瀬神父の本には少なからず良い学びをいただきました。これはイエスさまが悪魔の誘惑を受けられた箇所についての一つの解釈ですが、今日、教会のカルト化に心配の声が聞こえる時代に、大切な指摘ではないかと思いました。
正統的信仰に生きるキリスト教会は、ニカイヤ・コンスタンティノポリス信条、あるいは使徒信条を、信仰の基準としています。この信条を告白しない、あるいはできない教会は「異端」ということになります。しかし、この正統的な信仰告白をしている教会において、様々な問題が生まれているというのが、今日の教会の問題ではないかと思います。その問題の一つに「教会のカルト化」があると思います。
10年ほど前に恩師に勧められて読んだ、『現代人のための教理史ガイド-教理を擁護する』(棚村重行)によると、正統的信仰は、自動車で言うとガソリンのようなものです。ガソリンの純度が高いと、自動車にも環境にも良いが、純度が低いと、つまり不純物が混じっていたり、ガソリンでなかったり(ディーゼル車は、軽油ですが、灯油でも走らせることが可能と聞いたことがあります)すると、排気ガスが汚れて環境を破壊し、自動車自体もエンジンを壊してしまいます。そのように、信仰の教理がおかしいと、周りの人々、さらには社会全体に悪影響を与え、自分自身もその人生を壊してしまう、ということです。
しかし今日の教会の問題は、このガソリンに例えられている信仰の教理は、純粋で大丈夫、つまり異端ではないのですが、教会組織のあり方や、勧誘の仕方、信仰のあり方に様々な問題が見えているということです。それも信仰の教理の問題であるということもできますが、表面的に信条に照らしているだけでは、その問題点は分からないような気がします。それを「教会のカルト化」と位置付けて考えて見ると、見えてくる点があるのではないかと思いました。
確かに使徒信条などを礼拝でとなえ、三位一体の神さまを信じています。しかしその信仰生活、教会の運営に、様々な問題が現れ、それこそ環境破壊と自分のエンジンの破壊が起こっているのではないかと危惧するのです。
今日、私たちの教会は、富、知恵、自己実現を、偶像化していないでしょうか。
もし教会が、一つの目標を決め、それに従わないものは不信仰である、などという全体主義を語り始めたならば、そこにカルト化が起こっていると考えざるを得ないのかもしれません。