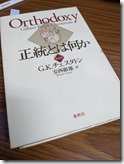海の中に、断崖に囲まれた小島があり、島の上は平らな草原になっていて、そこで子供たちは遊んでいる。断崖のへりに壁がぐるりと立っている間は、子供たちは心の底から奔放にふざけまわり、どんな子供部屋もかなわないほどやかましく遊んでも安心だった。ところがその壁が急に壊され、断崖の危険がむき出しになってしまった。子供たちは海に落っこちはしなかったけれども、昔の友だちが彼らのところへ帰って来てみると、子供たちはみな、恐ろしさのあまり島の真中に身を寄せ合ってかたまっていた。彼らの歌声はもう絶えて聞こえることはなかったのである。
(チェスタトン、『正統とは何か』、266頁)
教会には、二千年の教会の歩みの中で、培われ、育まれ、また確認されてきた教理や教義があります。その教理や教義を宣べ伝えるために、教職が立てられてきました。プロテスタント教会が生まれ、その中の急進的なグループの中には、この教理、教義、そして教職、あるいは教職制を否定するかのような信仰生活を語るものも生まれてきました。チェスタトンは教理、教義、教職制は、自分たちを恐怖から守っていた「壁」であり大切なものであると語ります。人間は自由を求めて、その「壁」を取り除こうとしたけれども、かえって不自由になっている、と語ります。
暗闇の中を自由に歩け、と言われてもかえって不自由でしょう。私たちは、自分が見えている、と自負しているときは、規則やルール、それを押しつけるかに見える先生たち、指導者たちをうっとうしく感じます。それがなければもっと自由なのに、と。しかし自分が見えていない者である、暗闇の中に、断崖絶壁に囲まれた小島の草原にいることを知ったならば、この規則やルール、そしてそれを指導してくれる多くの先生たち、指導者たちを感謝します。その「壁」があるので、安心して自由に生きることができるからです。
教会にもさまざまなルールがあります。教憲、教規、そして宗教法人の関係の規則と、大きく三つのルールがあります。これに加えて総会運営の細則、いくつものグループ内での規則、などなど。それらは信仰者を縛るものではなく、信仰者が自由に信仰生活、教会生活を送るための安全装置なのです。
キリスト教会の教理、教義は、この各教会の教憲、教規と深く関わっています。キリスト教会の教理や教義に反する教憲・教規を持つ教会があれば、それはキリスト教会ではありません。ですから教憲・教規というものは、各教会が独自に持つものではなく、できるだけ大きなグループ、もし教団や包括的な団体があれば、そこで持つべきものですね。洗礼の時に、問いかけることのなかでは、たいてい、教憲・教規については、その属するグループのものを問いかけることになっています。私たちの教会に当てはめると「あなたは、世界福音伝道会の教憲、教規、および東近江キリスト福音教会の規則に従い、その純潔と一致と平和のためにつとめることを約束しますか」と問いかけることになっています。であるにもかかわらず、ときどき各教会で独自と思えるような教憲・教規を持っていることに出会うと、団体から遣わされた牧師は、あぜんとすることになります。(笑) この辺がプロテスタント教会、特に福音派のおもしろいところですね。